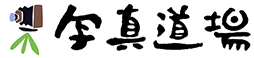ギャラリーMINを辞めてからは、名実共に無職。「フリー」というのも恥ずかしいのは、仕事をする積もりがなかったから。あ、こんなことを書いてしまうと罪になりますね。失業保険をもらっていましたからねぇ。すみません。
なんでもいいから「お金を稼ぐための仕事」はしたくなかったのですが、写真の周りにはいたかった。それだけの気持ちで生きていました。今、この歳になって思うのは、「写真の周りにいる」という気持ちがあったからこそ、前向きになれたのかもしれません。これがなく、お金のための仕事をすることを始めていたらいったいどうなっていたのか・・・。
フォトジャポンでアルバイトの面接官であり編集の基礎を教えてくださり、さまざまな先生たちに紹介してもくださった高橋周平さんは、フォトジャポン休刊を機に福武書店を辞めました。そのくらい、「写真」に深入りしてしまった、のでしょう。これは、写真の周りをうろつくだけの私にとっては、「写真」の磁力に引き込まれる人が増えることに対しては大変に嬉しかったのです。が、だからといって私は、高橋さんの後ろをついていくしか能がありませんでした。
フリーになった高橋さんは、フォトジャポン編集部時代に築いた人脈を活かし、写真に関する企画を立て、さまざまな出版社や会社に売り込みをし、編集実務もできるプロデューサー的な存在になっていきます。仕事をするつもりもない私は、この一部のお手伝いをするとこで、糊口をしのぐようになりました。「CAPA」のコラムの執筆の仕事を作ってくださったのも高橋さん。パルコで開催された「期待される写真家20人展」の企画を通して開催、2回目の実施の時に参加を促してくださったのも高橋さん。他にも、細々したお手伝いをさせていただき、ご自宅に宿泊させていただいたこともあります。
伊藤事務所のこと
「伊藤事務所」と書きますが、正式名称を思い出せません。事務所の名前はなかったのではないかなぁ。
確か、青山の骨董通り。ビルの2階、3坪あるかないか。真っ白の壁、前入居者が使っていただろう黒い洒落た机が4つ中央に配置されているだけの、実にスタイリッシュな空間でした。後に、部屋の中央に机があると導線が非常に悪いと感じた私は、誰の許可を取ることもなく勝手に机を壁に寄せたのですが、それでも誰からも文句を言われることはありませんでした。
事務所といっても関係している方々が一緒になって何かをすることが一義ではなく、それぞれが個人として事務所を共有していただけなのでしょう。詳しくはわからないままですが。
代表格は、当時飛ぶ鳥を落とす勢いだった写真評論家(後に写真史家を名乗るように)の伊藤俊治さん。そして高橋さん。写真家の北島敬三さん。事務所には関わっていなかったはずですが、大島洋さんも出入りしていたなぁ。それから、リブロポートの石原さん。イラストレーターの野末さん。私と同じ写真学校の先輩である河野さん。
誰かが何か大きな仕事を取ってきたから、なんとなく適材適所に仕事を割り振って実行。全員、フリーであって、やりたいことをやりたいようにやるだけ。それが終わったら、お金を山分けしてバラバラに。しばらくして別のプロジェクトが始まったら、てんでんに集まって仕事をこなすといった按配です。
なんとなくは、テレビドラマに出てくるような仕事の進め方であって、「こういう具合に仕事ができるんだ。」という事実にただただ驚き、その現場に居合わせたことにえもいえぬ喜びを感じたものです。
大きな仕事を任されたことで思い出すのは、伊藤俊治さんからの依頼。「花と緑の博覧会」で展示する写真の企画をまとめるために、知りうる限りの(芸術的な)写真を集め、コピーして整理する。というものでした。最初は意気込んで始めたのはいいのですが、その膨大な数と、作業の面倒さに、ほとんど煮え切らないまま期限を迎えたように思います。でもちゃんと、お金はいただきました。ずいぶんな金額だったはずですが、その金額に見合う仕事だったとは、今の今でも思えません。ごめんなさい。
『KULA』のこと
 『KULA』は、 クラ交易からとった言葉で、この詳細はこちら。この名を冠した写真情報のニュースペーパーを作りたい! と北島敬三さんが言い出したのです。こうした名付けをすること自体、ニュー・アカデミズムの時代ならではと、今にして。
『KULA』は、 クラ交易からとった言葉で、この詳細はこちら。この名を冠した写真情報のニュースペーパーを作りたい! と北島敬三さんが言い出したのです。こうした名付けをすること自体、ニュー・アカデミズムの時代ならではと、今にして。
伊藤さん、高橋さん、大島さんたちがこれに共鳴して作り始めたのです。港千尋さんも参加していました。私は、この原稿整理や著者とのやりとりなど、編集の下っぱ働きをすることになりました。いくつかの企業が広告を出してくださり、相応にお金は集まったはずですが、儲かるほどではなかったはず。渋谷などにあるアート系の書籍を扱う書店に出向き、この新聞を置いてもらうために、店頭に並べたりすることも私の役目でした。どんな仕事も始めてでしたので、相応の楽しさがありました。
ニュースペーパーについては、その理念は一緒にいて説明を受けているからなんとなくわかるものの、それぞれの企画の意味や内容を自分自身でわかっていたとは思えません。具体的に、誰に対して、何をどうしたいのか? は、よくわかりませんでした。ただ、立派な方々たちがやっていることだから、ついてけばなんとかなるんじゃなかろうか、という程度。ですから、多分、1号は私がかなり作業をしたのですが、2号以降は河野さんあたりがやってくださったように思います。
ニューヨークへ!
そうこうしていると、北島さんが「久門、ニューヨークに行こう!」といいだしたのです。何でも、四方田犬彦さんと一緒に本を作る企画があるらしく、その取材でニューヨークに行くといいます。なのでついてこないか、と。アシスタントとか、手伝いという言葉は一切なく、ただ、お供するだけ。なのでもちろん、ギャラとかはなし。旅費は自腹。
そう、北島敬三さんと言えば、1982年に白夜書房から出版された写真集「ニューヨーク」は、恐怖を感じるくらい過激でパワフルなモノクロのストリートスナップでつとに知られる写真家です。私も、会社員時代に購入していましたので、氏の申し出はまさに天佑のごとくでした。が、まったくお金がない懐事情も事実でしてその旨を伝えると、多少なら用立ててくれるというので、「じゃあ、行きます!」 と。
私は4×5カメラにフィルムなど撮影道具一式をそろえ楽しみにしていたのですが、飛行機に乗る日まで1週間を切ったころでした。北島さんが急に腹痛を訴える。あまりに酷いので病院に行けば、盲腸という診断。即入院、即手術。術後に、医者が「これが入っていました。」と、膿盆からピンセットで持ち上げた「石」は、直径1センチくらいあり、盆に落としたとたんカランと湿った音を立てて。これはこれは痛いはず、ですがさて、北島さんがこの状態だと私はいったい全体・・・。
結局、北島さんはフライトには間に合わず、私は未だお会いしたこともない四方田さんと二人でニューヨークに旅立つことに。
四方田さんは事情もご存知でしたし、ニューヨークも何度も訪れた経験もあり、たいへんに気さくな方でしたので心配ご無用。アンカレッジ経由の飛行機は、12時間以上のフライトで、乗客はすくなくガラガラの大韓航空。「ビールはサービスだからどんどん呑もう。スッチー(当時はCAとは呼ばなかった)には맥주(ぺくちゅー)っていえばいいんだよ」と教えてくださり、二人で何度も何度も注文して、挙げ句は床座りでベロベロになるまで飲み続けました。いやもう、今にしてみれば恥ずかしいことこのうえありませんが・・・。
ニューヨークはケネディ空港からドメスティック・エアラインに乗り換えラガーディア空港へ。深夜着。タクシーでマンハッタンに入りました。タクシーは後ろの席、左側に座っていたので、トライボロ橋からは夜景のビル群が水平線上に広がり、それはまさにきらびやかな銀河を間近に見ているようでした。
1989年、昭和63年の12月末。
昭和の終わりが刻一刻と近づいていました。