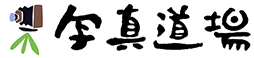「スナップ写真」(スナップしゃしん)とは、人物などの被写体を、自然な形や雰囲気のなかで早撮り(即興的撮影)した写真。 (wiki)
定義としては上で必要十分。で、当時のカメラ雑誌のコンテストの入賞作品のほとんどは、これでした。また、撮り方だけをいうと、報道写真の至るパパラッチ的な写真、屋外で撮るファッション写真や広告写真も、この延長線上にあるといえば、そういうこともできます。また、被写体に許可をとるかいなか? 被写体が喜ぶ写真かどうか? というと、今ではほとんど犯罪になりかねない撮影方法になります。
写真学校に入ったのが4月で、ゴールデンウィークをすぎたころに、浅草は三社祭を撮影しに行くのが学校の恒例行事。「祭り」ですから、カメラを持って、祭りそのものや観光客やお店の人などを無許可で撮影してもさほど問題になることはありません。しかし、赤の他人に許可なくレンズを向ける、のはかなり勇気が必要というか、撮られる側にしたら?? となることは確かであって、運が悪いと「何で撮るのか?」「何撮っとるんや!」「カメラ出せ、フィルム出せ!」「殴ったろうか!」的な展開になるし、そうなることが少しは予見されるので、やはり怖い。
この怖さを克服しろ! というのが、学校の課題の至上命題となっていました。
さすがに、今はあかんと思いますけれどね。
しかしまあ、人間とは面白いもので、こういうのをやり続けると間合いがわかる。文句を言う人と言わない人の区別ができるようになってきたりはします。こういうのがいつか役に立つ日が来るはず、という期待でがんばるわけですが、これができなくて嫌になった学生は多かったです。で、今にしてみれば彼らの方が正しかったわけですが、仕事を辞めて(半分は人間辞めたような気になっていた)私のような立場では、これが、これこそが頼みの綱であったのです。
「スナップ」の意義がなくなってきた最も大きな要素は、カメラの進化で誰でも撮影できるようになったことに付きます。写真は自分たちで撮れるようになると、人に撮られることの意味合いが変わってくる。自分の肖像に関する意識も変化していく、という大きな流れ。もちろんその前段として、私のような人間が「スナップ」を撮るようになったのもカメラの進化のお蔭なのですが。
つまるところ、カメラの進化の過程で、写真の意義がどんどん変わってくること。つまり、写真の意義そのものに普遍的なものなどない(という見方もできる)ことに自覚的になれるかどうか、が、写真の世界で生き残っていけるかどうかの分水嶺なんじゃないか、というのはちょっと話が広がりすぎ。
前回、牛腸さんや春日さんについてちょっと触れましたが、当時、全ての写真は「スナップ写真」に通ず的なニュアンスがあって、これは私個人の考えというよりも、カメラ雑誌や学校(とりわけ綜合写真)の底流になっていたことだと思うし、カメラ業界、報道、広告全てが、「スナップ写真」を軸に動いていたといえば、そのように見ることが可能でした。
ロバート・フランクの「アメリカ人」、高梨豊の「東京人」、東松照明の「太陽の鉛筆」、荒木経惟の「さっちん」・・・時代を少し遡れば、木村伊兵衛はスナップの名士だったし、土門拳の筑豊だってスナップ写真の範疇なのです。
さらに遡れば、報道としてのスナップ写真が源流となるのでしょうが、もともと感度が低い感光材料で大きなカメラで撮影するのは一つはイベントになっていたのが、感度が高く、カメラが小型中判レベル)になることで「早撮り」ができるようになり、さらにカメラが小さく(35㎜)なることで被写体に気付かれないように撮影できるようになってそれが人々の「裸のような自然な表情」に見えるようになってきた・・・という流れ。
このように考えると、いわゆる写真表現は、写真家の芸術的な個性ではなく、カメラの進化とそれに応じて変化してきた人々の意識を半歩先んずる写真家の感性によるものではないか、という見方も可能になってきます。まあ、鶏か卵かみたいな話にすぎませんが・・・。しかし、とりわけNHK日曜美術館的に、「写真家の個性がそれを表現した」という言い方が、まさに喉に刺さった小骨のような違和感で引っかかってしまうのは、こういう具合に自分が考えるからでもあるのです。
閑話休題。
校長の、重森 弘淹(しげもり こうえん)さんについてはwikiにも詳しく書かれています。名前が凄いんですよね。出自もそうですが。「1926年7月27日(大正15年・昭和元年)生まれ。1958年「東京フォトスクール」を創立、1960年東京綜合写真専門学校と名称を変えて発展させ、自らの写真美学や批評精神を展開しつつ、写真家の育成に情熱を注いだ。」
前身の学校を設立したのは32歳の時と若そうに思えますが、まあ、今の感覚でいうなら40~50歳くらいの感覚でしょうか。昭和35(1960)年の平均寿命は、男性65.32年、女性70.19年ですから。
「1955年頃から、カメラ雑誌を中心に写真の評論活動を開始し、当時隆盛をきわめていた「リアリズム写真運動」を批判的に継承しつつ、東松照明や奈良原一高らによる新しい写真表現の登場を支持し、さらに現代写真の始まりを告げるウィリアム・クライン、ロバート・フランクらの仕事をいち早く紹介、評論する」とあります。社会的な状況からすると、戦後から高度成長期に至る過程で、古いモノがどんどん破壊され、新しい都市が生まれるそのまっただ中で、普及し始めたカメラを手に「新しい写真表現」が模索されだした時代です。カメラメーカーはカメラを売るために、フィルムメーカーはフィルねを売るために、雑誌社は雑誌を売るために、一般消費者は自分たちの未来を信じて今を記録しようとカメラを買った時代。
「家族アルバム」が普及するのもこの時代ですが、60年安保などの社会的な運動、地方から上京した金の卵と、勉学を目的として大学に入ったのにマスプロのなかで欲求不満が高くなり、その意識が社会運動に向かわせたり、内向的になったり・・・。こういう環境の中で「新しい写真表現」を求めるなら、当然といえば当然の成り行きといえます。
重森さんは、こうした若い人々に一つの方向づけをして「写真家を育てた」という言い方になるのでしょうが、悪意のある見方をするなら、重森さんの元で育った若い人々は重森さんのコマとして動くことを陰にも陽にも要請されていたといえます。もちろん、それは本人たちも望んだことでしょうし、それによる恩恵も十分過ぎるほどあったのだろうと推測するわけですが。ただ、私自身は、春日さんの自死をこの悲劇の一つとして認識してしまう。そしてまた、日本とりわけ東京の都市化がさらに進み、カメラがさらに普及していく中で、重森さんの思考の射程では捕らえられなくなりはじめたのが、私が入学した1880年の中頃、つまりバブル景気の始まり頃でなかったかと思うのです。