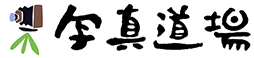前回の更新が1月だったので、8カ月ぶり。ある程度目標地点が見えてきたと思ったら、そこと現在地の落差というか距離の長さに負けて、頓挫しておりました。
そんなわけでまだ十分な整理もできていなのですが、続けます。
写真学校に入った1984年は、ニューアカデミズム・ブーム前夜(浅田彰『構造と力』は1983年刊行)であって、同級生や先輩の一部の影響もあり、ずいぶんこの系統の本を読みました。ロラン・バルトの記号論、ソシュールの現象論、デリダの脱構築・・あれこれ。ぜんぜんわかっちゃいなかったのですけれど、読むだけは読みました。
そんな時代ということもあったでしょうし、アサヒカメラや日本カメラ、カメラ毎日などしか情報源のない四国から上京して、重森校長がまだ健在であった写真学校で学ぶようになって、「写真」のとらえかたが大きく変わっていったのでしょう。四国の友人知人に、自分が学んでいる「写真」を語るのがなかなか難しいように感じだしました。どうしても、「標準語(的なるもの)」でしかしゃべれないのです。こういうのは、なんかいやだなと思い、写真のことはあまり話題にしなくなりました。
そもそも論的な話をすると、趣味としての写真の一つの目標地点がカメラ雑誌のコンテスト入賞だっとして、そのコンテストの写真の良さを写真か趣味ではない友人知人家族に話すことができるか? というと、これがなかなかできません。
多くの「趣味」はそのようなものかもしれません。
また、これは写真学校に入る前から思っていたことですけれど、子供の頃から、いわゆる写真館で撮影した写真って、「なんか違うよなぁ」「ぜんぜん綺麗に見えないし」と思ってもいたのです。こうした点でいうと、いわゆる雑誌に掲載されている写真(広告や記事)の方が、リアルに感じていました。つまり、地域のプロのカメラマンの代表か写真館だったとして、これはもう全然眼中になく、雑誌や写真集でみる写真を撮影するカメラマンの方が格上でしかも身近にいない分、雲上の人のように憧れていたのです。カメラ雑誌の写真は、これらの両方とも違って、カメラを趣味にする人のための、いわば同人誌的な価値観で身近だったのでしょう。
篠山紀信と荒木経惟あたりが、私の時代のスタア。とりわけ篠山紀信は国民的に知られるカメラマンで、新しい写真の美の基準となっていたといっていいでしょう。視線の価値観が篠山紀信の写真でできてしまったうら若き青少年にとって、旧来の写真館の写真は「古くさいイメージ」に見えたとしても不思議ではありません。
高専の頃だったか、親戚のお姉さんが成人を迎えて写真を撮影してきたというので、その写真を見に行ったことがありました。普段ではない化粧をして、和服を着て、ポーズを決めて写真に収まったその姿を観ても、なんにも綺麗だと感じませんでした。すると、一緒に観ていた別のいとこの母親が「着物は綺麗だわねぇ」と、我が意を得たり的な発言をして、私は心の中で拍手喝采を送ったのですが、その場の雰囲気は覚えていません。
話を戻しましょう。
つまるところ、「写真」と一言にいっても、一般の人が日常的に撮影する家族や旅行の写真、カメラ雑誌に代表される趣味の写真、写真館のプロの写真、メディアにみるプロ(広告、報道、スポーツ)の写真、さらに「芸術」としての写真、が、それぞれに独立して、お互いに重なり合うところがほとんどない、というのが現実なのです。
だから、言葉が通じない、ということになる。
写真学校の正式名称は、「東京綜合写真芸術専門学校」であって、「芸術写真」が目指され、その理念の基本線は重森弘淹が描いたいわく言い難い「何か」です。それが「何か」は、だれもわかりません。みんなでよってたかって、だれもわからない「何か」を追いかけていたのではないか、と今、私は強く疑います。
当時の目標は、「太陽賞」受賞であったし、広告ではないドキュメント(的な)作家として自立することだったり、当時雨後の筍のようにできた写真ギャラリーや写真美術館で「作品」を展示される芸術写真家になることで、学校の研究生や卒業生の一部がそのようになったことが、大きく喧伝されていました。と同時に、これらのどれとも違う、アメリカのアートシーンで有名になった「ニューカラー」「ニュートポグラフ」「テイクからメイクへ」といった標語とイメージを追いかけるように次から次への消費するだけ。
なので結局のところ、そのような「立場」に立てたことが「よい写真家」になれた証であって、一般の人たちが写真を観て「すごい」とか「いいな」とか思えるようなものではありません。逆にいえば、一般の人には難解であればあるほど、関係内部の人たちは「すごい」というようなもの。
もっとも、一般受けするものがよいわけではないので、どのような文化もこうした傾向があるし、あるべきだとは思います。が、しかし、個人的な意志の傾向として、私はもうついていけないな、と思ったし、どちらかというと「面白くないな」と否定的見解をとるようにもなっていったのです。
そうこうしながら知恵がつくだけ、あれもだめ、これもだめ、面白くないものばかり、と不平不満の固まりになって、自分ではなに一つやらない、やれない体たらくになってしまうのが関の山。にしても、カメラ雑誌やギャラリーや美術館が元気であれば続ける道もあるのですが、そういうリソースがぜんぶなくなってしまったのが、今、なんでしょう。
話題はちょっと変わりますが、半年ほど前に写真学校の現校長や同級生に再会して、少し話をしたのですが、今の写真学校は半数くらいが中国人になっているんじゃないか、とのこと。少子化に大学が増えたこともあるし、学校にいかなくてもカメラマンになるのは簡単にできるようになって、日本人学生はどんどん減り、経営が成り立たなくなりつつあるのは確実でした。ところが運良く中国のお金持ちのご子息が日本留学の口実で大量に入学してくれるようになって経営が続けられたのだとか。
もちろん、中国の政治的状況から逃げ出すこともあります。なおかつ彼らはお金に余裕がありますから、高級外車に乗って学校に来るような学生も少なくないそうで、数年経って卒業すると、また別の専門学校に入り直して、延々留学生を続けるといいます。お金に余裕がありますから、いろいろな所に顔を出す内、いい仕事を見つける人も少なくはないでしょう。この点、日本の学生はお金がなく将来不安もある世代なので、「とにかく正社員になる」ことを目標としている、とか。「われわれの時代は、就職なんかしたくないから、写真学校にいって、フリーになっていたのにねぇ」と、ちょっと昔を懐かしんだりしたわけですが、これは一重に景気が悪いせい、でしかないでしょう。私たちの、古き良き時代を基準にしていたのでは、これから先はやっていけないことは確実です。