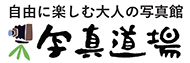「PHOTO JAPON」は、1983年11月号創刊ですから、10月発売。翌年の3月に会社を辞めて上京する、そんな端境期の雑誌です。
左の写真から、古書販売の「ニ手舎(ニテシャ)」による「PHOTO JAPON」のページに行けます。今、表紙を見なおして、創刊号は買って最近まで持っていたことを思い出しました。写真も記事も、キレイで上品、欧米のアートってこんな感じ? というニュアンスで、しばらくは買い続けたはずです。しかし、なんだか、記憶が薄いんですよね。手元に置いてあって、見直せば違うかもしれません。(カメラ毎日はスクラップブックがあって、時々見直していたせいで記憶が濃いのでしょう。)
左のページは1~23号までの全号、次のページには24~35号までが歯抜けで掲載されています。表紙をクリックすると目次も見られるので、ありがたいです。
表紙を見直して、明らかに記憶に残っているのは、30号(86年4月)のシャーデーから、35号(86年9月号)のMENS企画まで。なぜ覚えているかというと、この期間、フォトジャポン編集部でアルバイトをしていたから。
日付も記憶と符号します。
写真学校は2年で卒業し、86年の4月から研究科に進んだのですが、卒業間もないころ研究室に遊びに行った時、たまたま平木 収さんがいらして、「久門、編集部でアルバイトしていみないか?」 という問いかけに、「はい」と即答したのでした。私を選んで、ということではなく、たまたま部屋に入って来たのが私だっからという程度だったと思います。
高橋周平さんのこと
教えてもらった編集部に電話をし、九段下にある福武書店の上層階の編集部に面接に行きました。
いやね、福武書店は現在のベネッセコーポレーションですが、当時から、女性社員が多いことでしられている企業でして、ビル一階、正面入ってまっすぐ突き当たったところにあるエレベータに乗ると、まあ、香水の臭いがプンプンしていましてねぇ、どこの花園に迷い込んだのかと思いましたよ。
で、アルバイトの面接官は高橋周平さん。今でも思い出すのは、面接時に聞いた「これからの編集者ってのはね、歌って踊れなきャ」っていう一言。
それから勤め始めてしばらくして、著者に伝える締め切り日はそうとうサバを読んでいる話になって、「いやね、編集者はウソツキの始まりだからね」というのも覚えています。
あともう一つ、編集者としていろいな写真家に会う中で、「お前は写真がわかってない! って怒られるんだけどさぁ。その写真っていうのを誰も教えてくれないだよねー」、というのも強烈でした。これは本当に含蓄がある言葉でして、当時の写真家および学校の先生なども、「自分が考える、ないしは社会的にある(芸術)写真とはこれこれこういうものだ」ということを、やさしく説明することができないのです。
いい解釈をするなら、「言葉で説明できるくらいなら写真を撮って見せる必要はない」ということになるんでしょうが、なにしろ自分で説明できない(おそらく当人が一番わかっていない)から、「お前はわかっちゃいない!」という言葉しかでないという一面は確かにあったのだろうと思います。結果、その意味や価値を伝えるには、一子相伝的になるしかなく、だから師匠ー弟子みたいな関係が好まれたのでしょう。こういう体質は、今の写真の世界でも時折感じることがありますが、まあ、世の中全般にも、そして私自身の中にもあるようにも感じます。