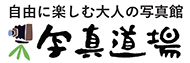これはアサヒカメラ 1882年、5月号の表紙です。
表紙に記載された特集は下記。
木村伊兵衛賞受賞第1作。「きむらいへえ」と読みますが、今、そこそこ古い写真関係者でなければ知らないかもしれません。第7回(1981年度)のこの賞に、渡辺兼人「既視の街」が選ばれて、その次の作品がこの雑誌て発表されたわけです。渡辺兼人は「わたなべかねんど」と読みます。人形作家の四谷シモンさんの実弟。
この号に、氏がでていたとは、今、表紙を眺めながら初めてわかったような気がします。私、この2年後の1984年4月に、東京綜合写真専門学校に入学するのですが、そこの教師でもありました。直接お会いして話をするようになったのは2年生以降ですから、ゆうに3年はあり、覚えがなかったとしても仕方はないでしょう。氏の作品は、なんというか、ごく普通に見える風景写真ですが、なぜこれがいいかは難解という、アマチュアにはわかりにくいものでしたから。
他に、高梨豊さん、森山大道さんの名もあります。高梨さんもまた、今、あまり振り返られることはない写真家ですが、1974年に発表した『東京人』は、写真学校の校長であった重森 弘淹さんがほとんどバイブルのように語られてました。今、思えば、1958年に発表されたロバート・フランクの『ジ・アメリカンズ』の日本版のよう。写真学校のことは、またいずれ整理しようと思います。

ともあれ、なぜこの号を一冊まるごと残しているかというと、何を隠そう、月例コンテストの「初級写真部門」で1位に輝いたからなんです。いやあ、嬉しかったなぁ。
本来、月例コンテストというのは、アマチュア諸氏の技術向上の目的も含めて実施されているもので、1年を通して作品を応募し続け、年間を通して優秀なアマチュアには特別な賞が授与される仕組みです。私は、思いついた時に時々応募してみるくらいでした。
タイトルは、「夏を想いて」とあり、応募時は「夏を想ひて」と書いたはずですが、校正されちゃった。住所は「香川県・宇多津町」とあります。当時は、香川県宇多津町の四国電力の寮に住んでいて、この写真は丸亀城の上から丸亀高校のグランドを見下ろすように撮影したものです。寮の部屋を暗室にして、自分で現像・プリントしていたのです。その程度には熱心に頑張っていました。写真屋の親父とは話はするもののあんまり頼りにもならず、誰に教わるということもなく、入る情報は写真雑誌と関連書籍だけ。
カメラは、キヤノンAE-1、135mm。トライX。普及型一眼レフの銘機。フィルム名も懐かしいなぁ。
選者は、丹野 清志さん。選評が詩的でいいんですよ。
「夏の甲子園に向かって寒空の中、ひそり素振り。なんていうと型どおりの図式になってくるのだが、ぱっと見たぼくはそんな解説は考えなかった。キャビネサイズのちいさなプリントではあるけれど、光と影と、やわらかいスポットライトが当たっているような動きの中に、詩を感じたのだ。そんなのアマイよォ、と言う人がいるかもしれない。でも、ふっと爽やかなメロディを聴くような時もあっていいではないか、と思うのだ。ふんわり気持ちをゆさぶったのは、モノクローム独特のトーンの味わいにもあった。それは単にプリントがきれいだということではない。きめの細かいトーンが、ぴったり写真に合っていたのだ。その印象は、印刷されるとどうなるかわからないが。プリントが微粒子であれ、素粒子であれ、面白いのが撮れた、上手く写ったというだけでは黒白画像だ。ピコピコパチリで写ってしまうメカトロニクスの時代の今、モノクロームのトーンを見直してみたい。」
なんか、泣けてくる・・・。一枚の写真でここまで想像力を膨らませて文章を書けるってすごい。そうそう。数年前だか、思い立って、日本カメラの元編集者に丹野さんの連絡先を聞き、このときの感謝の手紙を送ったのです。「ご活躍は、いつも拝見しております。」と返事が来て、またまた感謝。
上の写真の右側は印刷。左側は当時予備で作った実物のプリント。印刷はずいぶんコントラストが高くなっているんだなぁ、とも思うけれど、送ったプリントが左のとまったく同じでもないので、程度の差ははっきりしません。プリントは定着不足もあったようで、端が少し黄ばんでいます。「ちゃんとせえよ」と当時の自分に言ってやりたい。