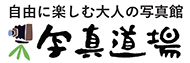今年の8月に発行された『日本画像学会誌 270号』に、「写真は夢を写すか?」というタイトルで文章を載せていただきました。何年も前から構想だけはあったにも関わらず、どこからどう手を付けてよいものやら迷いに迷ってのびのびにしていたテーマに、やっと一つの区切りをつけられたいい記事になったなぁ、と自画自賛しているのですが、しかしこれこそが次のステップへの始まりでもあるわけで、これを意識するととにかく気持ちが晴れやかになるわけでなし。やっぱり、どこからどう始めてよいのか、相も変わらず迷い続けているわけです。
まあね、歳ってのもあるのだとは思うのですよ。勢いってのがない。えいやぁ、って、後先考えずにとにかく始めようって気分にならないのです。こうして人は、少しずつ死に向かってゆるやかな坂を下っていくのだな。などと考えていると、28の頃に西城さんにいわれた「私たちに必要なのは、新しい哲学なのです」という言葉が、じわじわ実感を伴いつつ我が身に迫ってくるようになってきました。(こちら参照。)ああ、あの時、西城さんはこういうことをいわんとしていたのかもしれない、と。
しかし、このままやり残してしまうのも癪に障るので、もう一頑張りくらいはしてみようと決意を新たに。まずは、「写真は夢を写すか?」に少し手を入れて採録します。
1. はじめに
よく知られるよう、20世紀終盤からの写真業界は惨憺たる状況であった。1983年にアグファ・ゲバルトがカメラ事業から撤退、2005年には破産してフィルムの生産も終了。2004年にはイルフォードも破産。2012年にはイーストマン・コダックが経営破綻。国内では、2003年にミルノタがコニカに合併されてコニカミノルタになる。しかし2006年にコニカミノルタはカメラ事業から撤退し、カメラブランド「α」はソニーに譲渡された。2020年にはオリンパスがカメラ事業から撤退、OMデジタルソリューションズに事業譲渡、といった具合。もちろん、カメラ業界に連なる中小企業の多くも姿を消した。

Fig. 1
カメラの出荷総数(Fig.1)を見てもこれは明らかで、2000年を境にフィルムカメラからデジタルカメラに完全に移行した。2000年カメラ付携帯電話J-PHONEが発売。2007年にはiPhoneが発売(国内販売は2008年)されて、これ以降、コンパクトデジカメは急激に売れなくなっていく1)。
目を転じて、プロ・ハイアマチュア向けの一眼レフ、中・大判、デジタル一眼レフ、ミラーレス一眼の出荷台数(Fig.2)を見ると、2020年頃を境にミラーレス一眼が持ち直しているように見えるが、実際にはムービー撮影用途(同価格帯のビデオカメラよりもボケを活かした美しい映像が撮影できる)がシェアを伸ばしているのであって、写真撮影といった意味では、業務用か、そうとうマニアックな機材になっている。

Fig. 2
しかしその裏では、携帯やスマホの普及とカメラ機能の高品位化もあり、人々が撮影する写真の点数そのものは、2000年以降、爆発的に増大しているのである。
写真がフィルムからデジタルに変わって、誰もが簡単にキレイな画像をほとんどコストゼロで撮影できるようになり、SNS (social networking service) を使って多くの人に見せることができるようになりました、というのはたやすい。しかしいったい、一人一人の心の中にある「写真」のイメージは変わったのか、変わっていないのか? 変わったとしたらどのように変わったのか? なぜ変わったのか? を写真の戦後史をひもときながら大まかに俯瞰してみたい。
2. 写真機からカメラへ、そしてケータイからスマホへ
カメラは光学レンズを使ってできた像を化学的(電子的)に記録する装置である。特殊な例を除けば、レンズの焦点距離で画角を決め、フィルム(センサー)とレンズの間隔を調整してピントを合せ、レンズの口径(絞り)とシャッタースピードで写真写りの明るさを調整する。絞りでボケの大きさが、シャッタースピードでブレの大きさが変わる。かつてはこれらを全て経験とカンを頼りに手動で設定する必要があったのだが、技術の進化によって、写真撮影はどんどん自動化してきた。
ここで、カメラの自動化の流れを大まかに並べてみる。AE(automatic exposure)は自動露出、AF(auto focus)は自動焦点である。各タイトルの右側には主なユーザー層を記した。
- 手動カメラ・・・写真が趣味のマニアと職業写真家
- 1960年 ニコンF(マニュアルのシステム一眼レフカメラ)
- AEコンパクトカメラ・・・父親
- 1961年 オリンパスPEN(シャッター優先AEコンパクトカメラ)
1965年 ヤシカELECTRO35(絞り優先AEコンパクトカメラ)
- AE一眼レフ・・・青少年男子
1976年 キヤノンAE-1(シャッター優先AE一眼レフカメラ)
1978年 キヤノンA-1(シャッター優先・絞り優先・プログラムAE一眼レフカメラ)
- AFカメラ・・・一般、高齢者
- 1977年 コニカC35・ジャスピンコニカ(AF搭載のコンパクトカメラ)
- 1985年 ミノルタα-7000(AF一眼レフカメラ)
- 軽量・コンパクト・スタイリッシュなカメラ・・・主婦、独身女性、女子高生
- 1986年 フジカラー 写ルンです(レンズ付きフィルム)
- 1991年 オリンパス μ(スタイリッシュなコンパクトカメラ)
- 1993年 キヤノン EOS-Kiss(軽量コンパクトな一眼レフカメラ)
- デジタルカメラ・・・PCユーザー(eコマース)、職業写真家
- 1996年 キヤノンPowerShot 600(デジタルコンパクトカメラ)
- 1999年 ニコン D1(デジタル一眼レフ)
- 携帯・スマホ・・・女子高生、一般
- 2000年 J-PHONE(カメラ付き携帯電話)
- 2008年 iPhone (スマートフォン)
どの機種にどのような思い出があるか? で年齢層が決まりそうだが、それぞれの段階でカメラのユーザー層が、経済的に余裕のある男性から、青少年男性へ、そして高齢者、主婦や独身女性へ、女子高生へと広がってきた。
カメラメーカーのwebサイトには歴代のカメラが紹介されているが、1960年代までの機能優先で黒く無骨なカメラから、1970年代には機能をカジュアルに昇華させたデザインになり、1980年後半には曲線を活かしたスタイリッシュさでカラーも多様になっていることがわかる。
ちなみに、オリンパスから新発売された機種の数を年代別に分けると、1960年代19機種、1970年代13機種、1980年代28機種、1990年代97機種、2000年代152機種、2010年台96機種、2020年代2機種となっている。2000年代は毎月1台以上の新機種が登場している勘定であって、今振り返ってみれば、異常事態としかいいようがない2)。
こうした多様なカメラを開発・販売することは、写真のユーザー層を拡張することと裏腹であって、メーカーはその広告のイメージや媒体を変えてきたわけで、この一端はカメラ雑誌の広告にも見ることができる。
3. 何を撮るか? どう撮るか?(カメラ雑誌の変遷)
カメラ店やメディアなどを通して見るカメラの広告の世界観に憧れ、やっとカメラを手にする。箱を開け、恐る恐るカメラを取り出し、レンズや電池を組み込み、ファインダーを覗く。誰かがいっていたように、カメラを持つことでいつもの日常が新鮮に見えるかのような気がする・・のは、たかだか数日でなかったか?
そもそも、現実のファインダーの中に見えるのはいつもの日常に過ぎない。しかもカメラに数多くあるボタンやダイヤルはいつ、どのように触ればよいのかわからない。
こうした難題を解決すべく登場したのが、カメラ雑誌である。以下に戦後の代表的なものを創刊年順に整理してみる(名称は創刊時)。これらは基本的に、著名写真家の作品(理想のお手本)、カメラの新機種や技術、撮影ノウハウの紹介(宣伝)に加え、読者のコンテストの受賞作品(身近なお手本)で構成されている。
- アサヒカメラ(朝日新聞社)・・・・・・・1926年創刊 2020年休刊
- 日本カメラ(日本カメラ社)・・・・・・・1950年創刊 2021年休刊
- カメラ毎日(毎日新聞社)・・・・・・・・1954年創刊 1985年休刊
- 月刊カメラマン(モーターマガジン社)・・1978年創刊 2020年休刊
- CAPA(学研)・・・・・・・・・・・・・1981年創刊 現行
- デジタルカメラマガジン(インプレス)・・1997年創刊 現行
- デジタル・フォトテクニック(玄光社)・・2005年創刊 2021年休刊
これらに掲載されたカメラの広告から言えるのは、1960年より前はカメラの特徴がわかればよくて、1960年代になると高性能、高級感を演出するような写真が多用されるようになり、1970年代は青少年向けらしく女性アイドルやモデルが起用され、海外旅行やゴルフなどの贅沢な趣味を連想させるようになる。1980年以降は女性向けのカメラ雑誌やムックも増えて女性が撮る側に回り、女性誌などでの写真撮影の企画も増えていった。が、次第にカメラのユーザーの母数が少なくなったら、雑誌の使命も終えるのは道理である。
ところで読者がカメラ雑誌から得る情報は、撮影技術だけではなく、何を撮ればよいのか?どのように撮ればよいのか?といった写真のイメージの価値判断であった。つまり、カメラ雑誌はカメラの売り上げを伸ばすために世界の見方を提示し、教育してきた側面がある。枠組みが先に決まっているので、その中で序列をつけて競争を促すコンテストは、カメラへの欲望をさらに高める効果もあったろう。
こうしたカメラ雑誌以外に、写楽、PHOTO JAPON、deja-vu、IMA、GENICなど、写真コンテストを排し、アーティスティックな写真を鑑賞したり、写真を考える、という内容の雑誌は、だいたいが短命に終わっている。逆に、「写真」を見る楽しさという意味では、スクープやゴシップで構成されたFOCUS(1981-2001)などの雑誌の方は一世を風靡した。が、この役目もインターネットにお株を奪われてしまった。
 カメラ毎日創刊号(1954年)の表紙
カメラ毎日創刊号(1954年)の表紙
 同上のミノルタカメラの広告とコンテスト
同上のミノルタカメラの広告とコンテスト
 アサヒカメラ増刊(1975年)の表紙
アサヒカメラ増刊(1975年)の表紙
 同上のニコンとキヤノンの広告。(見開きで対抗させている)
同上のニコンとキヤノンの広告。(見開きで対抗させている)
 写楽創刊号(小学館 1980年)の表紙。
写楽創刊号(小学館 1980年)の表紙。
 同上のミノルタの広告。(宮崎美子さん)
同上のミノルタの広告。(宮崎美子さん)
 アサヒカメラ(1982年)
アサヒカメラ(1982年)
 アサヒカメラ(1982年)のニコンの広告
アサヒカメラ(1982年)のニコンの広告
 アサヒカメラ(1983年)
アサヒカメラ(1983年)
 アサヒカメラ(1983年)のキヤノンの広告(立木義浩+青木功)
アサヒカメラ(1983年)のキヤノンの広告(立木義浩+青木功)
 ミルノタCLEの広告(テキスタイルデザイナー/ファッションデザイナーのヨーガン・レールを起用)
ミルノタCLEの広告(テキスタイルデザイナー/ファッションデザイナーのヨーガン・レールを起用)
4. 写真家への登竜門
カメラやフィルムを一般の人が使えるようになったのは、高度成長期以降である。だから戦後間もないころまでは、よほど経済的に余裕のある人でない限り写真を撮ることができず、そもそも写真を職業とするのはその師弟に限られていた。
今でいう職業写真家(カメラマンやフォトグラファー)は、その需要であるメディア(新聞、雑誌、テレビ)と足並みを揃えながら登場するが、当初は目端が効いて経済的に余力のある人に限られ、こうした人々が職業写真家の第一世代を構成していくことなる。
さらに、長い高度成長期とオイルショック後のバブル経済までは銀塩カメラの全盛期であったので、メディアの発展とその需要に追いつくべく、後進の教育・発掘がなされる。写真学校や美術系大学での写真部の創設の他、一般に開かれた各種の賞は、名実ともに写真家への登竜門として知られる。年代は創設年と終了年を示す。
- 太陽賞(平凡社) 1964年~1999年
- 木村伊兵衛賞(朝日新聞社) 1975年~
- 伊奈信夫賞(ニコン) 1976年~
- 土門拳賞(毎日新聞) 1981年~
- 期待される若手写真家20人展(パルコ) 1989年~1990?年
- コニカ写真奨励賞(コニカ) 1990年~2017年
- キヤノン写真新世紀(キヤノン) 1991年~2021年
- ひとつぼ展(リクルート) 1992年~
太陽賞は、グラフジャーナル誌の「太陽」が開催していた賞で、ドキュメンタリーに軸足をおいたものに限られるとはいえ、無名の新人でも受賞可能で、とりわけ初期の頃はこれを受賞すれば写真家として認知され確実に仕事に結びついたようである。ちなみに、第一回の受賞者は荒木経惟である。
木村伊兵衛賞、伊奈信夫賞、土門拳賞は、どちらかといえば冠された名の写真家を憲章する要素が強く、ある程度の実績ある写真家に与えられるもの。
期待される若手写真家20人展よりも後の賞は、新人発掘の場として、全国の若手写真家に夢と希望を与えた。1990年前後はバブル景気時代の企業メセナ的意味合いもあったが、コニカ写真奨励賞、キヤノン写真新世紀、ひとつぼ展(現、1_WALL)のどれもが、多くの新人写真家を発掘している。写真学校や写真家の弟子を経由しない人に、プロへの道が開かれたわけだ。
とりわけ、1990年代後半からのガーリーフォトブームは、HIROMIX が1995年に写真新世紀で優秀賞を受賞したのが嚆矢である。続いて、蜷川美香は1996年にひとつぼ展でグランプリ、写真新世紀展で優秀賞、1998年にコニカ写真奨励賞を受賞する。2001年には、HIROMIX、長島有里江、蜷川実花の三人が木村伊兵衛賞を受賞したのが、おおきな弾みになった。Fig. 1に見る1995~1999年あたりにかけてのコンパクトカメラ(フィルム)の出荷台数の増加はガーリーフォトの影響だろうし、うがったものいいをすれば、キヤノンやコニカ、リクルートのこれらの賞は優れたマーケティングの好例といってよいだろう。
5. 写真はアートになりえたか?(写真ギャラリーと写真美術館)
絵画はそもそもオリジナル品が一つあって、他は模写か贋作ということになり、だからオリジナルは芸術品といってよいし、高価な値がつくことも常識だろう。しかし写真は、現実世界を光学的に写した画像でしかないし、原版があればいくらでも複製可能である。デジタルになると、品質の劣化もない。これを果たして、アートと呼んでよいのか?ということが写真家の根源的なコンプレックスであった。だから、写真美術館の成立は、多くの写真家の悲願であったのだ。
下記に日本における写真ギャラリーと写真を扱う主要な美術館を整理する。
- 写真ギャラリー
- 1978年 ツァイトフォトサロン(日本橋-現・国立)
- 1979年 p.g.i.(虎ノ門-現・東麻布)
- 1986年 ギャラリーMIN(学芸大学-現・閉廊)
- 1986年 プリンツ(大阪-現・閉廊)
- 1989年 パストレイズ(横浜-現・閉廊)
- 写真を扱う美術館
- 1983年 土門拳記念館
- 1985年 つくば写真美術館 (つくば万博にあわせて開館)
- 1988年 川崎市民ミュージアム (2019年台風による浸水のため閉館)
- 1989年 横浜美術館
- 1990年 東京都写真美術館 (一時施設として開館、1995年正式開館)
- 1992年 入江泰吉記念奈良市写真美術館
- 1995年 植田正治写真美術館
ツァイトフォトサロンは、石原悦朗(1978~2016)が開設した日本発の写真専門のギャラリーで、国内外を問わず、日本の若手写真家の発掘も行いながら写真作品を販売してきた。p.g.i.(フォトギャラリーインターナショナル)は、 アンセル・アダムスを代表とする高品位なオリジナルプリントを中心に扱いながら、その制作・展示機材などのサポートも行っている。
バブル時代には新しい写真ギャラリーや美術館が多く設立され、当初は意欲的な企画展も数多く開催された。しかし、新しい写真のムーブメントもなく、予算的な問題もあるようで、写真界を牽引していくような力は失っているように思う。公的な美術館はその内容は政治的・経済的な制約を強く受けるとはいえ、観客の動員と熱意をもって、アートとしての自由を謳歌してもらいたいものだが。
6. 写真館の変遷
写真館というと、お宮参り、七五三、入園・入学、成人・・・と、人生の節目で撮影する町のお店、というイメージが強いかもしれないが、全国的に町の写真館はどんどん姿を消している。写真館の歴史をざっくり整理してみる。
- 1960年頃~ 町の写真館・・・・商店街(写真師が撮影する伝統的な家族像)
- 1995年頃~ こども写真館・・・ショッピングモール(女性が撮影するこどもと家族)
- 2000年頃~ 一軒家スタジオ・・空き家、ロケ(契約フォトグラファーが撮るこども写真)
- 2020年頃~ セルフスタジオ・・商業施設や写真館の空きスペース(自分たちで撮る)
それぞれの時代における「家族のイメージ」の変化が見てとれると同時に、営業する場所も、商店街→ショッピングモール→空き家→空きスペース、と時代にそぐう変化をえていることがわかる。2000年以降はネット集客が主流になっていく。
さらに撮影者が、写真師(年配男性)→女性→契約フォトグラファー→自分たち、と変化してきたことにも注目したい。町の写真館は写真や着付けの知識のある男性が撮影していたが、戦前から営業していた歴史のある写真館や写真の学校で営業写真のノウハウを学ぶ必要があった。1970年以降の若い男性はメディアや広告写真に進んで行き、写真館は跡継ぎに限られたため、ここには出てこない。こども写真館に女性(保育の資格をもつ人も多かったという)を起用したのは、なにより子供のごきげんをとりやすいことがあるが、カメラや照明が使いやすくなったことがその背景にある。
契約フォトグラファーは写真を仕事にしたい初心者といってよく、撮影場所の背景セットと照明が整っていれば、カメラの使い方の基礎を学び、接客ができれば十分仕事になるようになったのである。ネット集客で契約フォトグラファーに撮影を依頼するビジネスモデルは、もはやフォトグラファーがギグワーク(短期的、単発な仕事)になりつつあることを示しているともいえる。さらに、セルフスタジオはもはやフォトグラファー不要のスタジオで、自分たちで自由に撮ることが可能になったのである。
こうしてみると、カメラの自動化と足並みをそろえて写真館での撮影者が変わってきたことは明らかなのだが、「家族のイメージ」が変化したのもカメラの自動化によって家庭内での撮影者が父親から若い男性へ、そして母親や女性へと変化してきたことが背景にあるといっても間違いにはならならないはずだ。
7. まとめ・写真は夢を写すか?
1960年以降のカメラや写真の歴史をたどってみると、1961年生まれの私自身の個人史とも重なる。一眼レフの普及、高性能化、デジタル化にいたるまで、まさに日本における写真の黄金期を生きていたのだと、今にして強く思う。
そして、たとえば自動車の普及が地域での生活スタイルを変えたように、カメラの普及が家族や私たち自身の自己イメージを変えたのではないか、という視点に立つなら、時代の移り変わりの様相が別の意味を帯びてくる。
これまで述べたように写真はフィルムからデジタルに変化してきたわけだが、どの時代を通してもそこに私たちはリアルな「夢」を見ることができた。1960年前後のリアリズムと政治の季節をへて、1970年代はアイドルや趣味にうつつをぬかし、80年代の狂乱の時代はアートに夢を見た。90年後半には男性の庇護のもと女性写真家が活躍し始め、2010年を過ぎる頃に彼女らは「自分たちのことは自分たちで決める」と反旗を翻す。私自分を含め多くの男の写真家はやせ我慢をするか、変化の速さに立ち往生している。それでも変化に対応すればなんとかなる、ように思ってきた。
しかし現在のスマホとSNSは、カメラを、人々を、監視・管理する道具へと矛先を変えたかのようである。街や施設のいたるところに防犯という目的の監視カメラがある。テレビに写る人々の顔にはボカしが入る。集合写真、とりわけ子供たちの顔は、一般に公開することが憚られる。人々は、なにかイベントがあるごとに、実物を見るよりも先にスマホを構えて画面を見つめる。生成AIは、言語で指示するだけで、現実に存在しないリアルな写真画像を比較的簡単に作り出すようになり、これはさらに進化を続けるのだろう。
どうなってしまうのか? その先にある夢はどんなものなのだろうか。
【参考文献】
1) https://www.cipa.jp/j/stats/dc.html (accessed 2024-06-11)
2)https://www.olympus.co.jp/technology/museum/camera/chronicle/?page=technology_museum (accessed 2024-06-11)
【図及び表の説明】
Fig.1 Compiled by the author from the Camera & Imaging Products Association’s statistics on digital camera production and shipments.1)
Fig.2 Compiled by the author from the Camera & Imaging Products Association’s statistics on digital camera production and shipments.1)