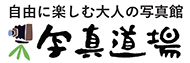資料を整理していたら、コダックなどのフィルムやカメラのカタログや啓蒙用のパンフレットのたぐいがごっそりでてきました。写真撮影や処理はデジタル一辺倒になってしまっていますので、これらはもはや無用の長物となりはてているわけですが、それでも、今見直すと懐かしさを超えて、写真の「技術」を学ぶことが、当時はとても面白かったことを思い出しました。
工業高専・電気工学科卒。国語、社会といった文系よりも、はるかに物理や数学などの理系の授業が好き。そうはいっても、化学はまったくもってチンプンカンプンだったので、私の中の写真の技術、というと、光学や工学のカメラ方面に向かうわけで、フィルムや現像の仕組みはあまりわからないづくここまで来てしまったのですが、それでも、相当に勉強しました。
もっとも、フィルムや現像液を開発したり、独自の技法を見いだすことを目...
Read More